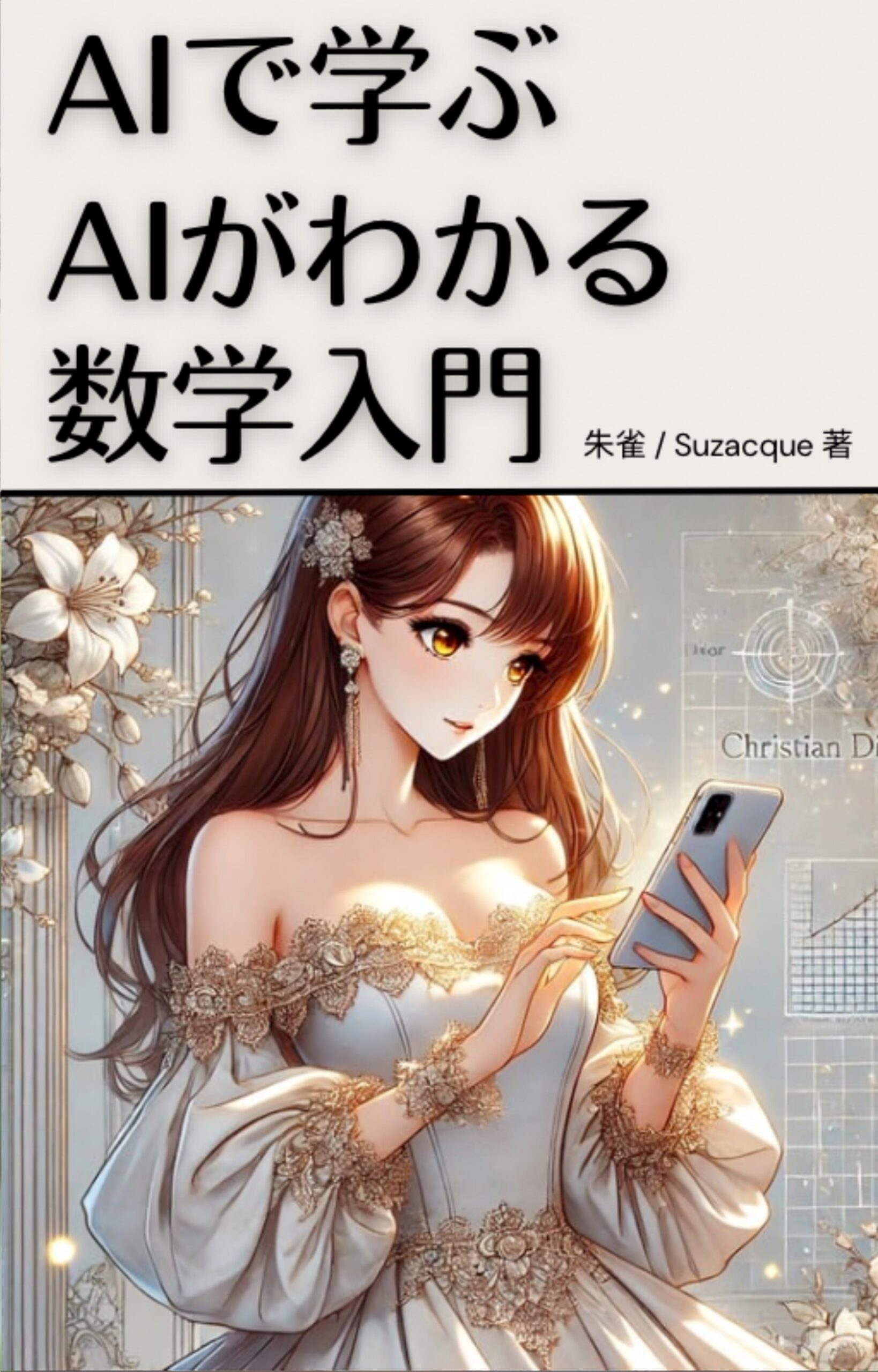経済成長理論の核心は、「生産性の持続的な向上によって国民所得(GDP)が長期的に拡大していく仕組みを解明すること」にあります。もう少し具体的に言うと、各時代の経済成長理論は以下の問いに答えようとしてきました。
- なぜ(あるいはどうやって)経済は成長するのか?
- 資本や労働力が増加すると生産量が増えることは直感的に分かりますが、それだけでは説明できない成長部分(総要素生産性、つまり技術進歩や効率化)はどのように生まれるのかを究明します。
- どのようにして技術進歩やイノベーションは起こるのか?
- 技術が外部から「与えられる」とみなす見方(ソロー・モデルなどの外生的成長理論)と、技術進歩も経済の内部要因(研究開発投資やヒトの知識蓄積など)から生まれるとみなす見方(内生的成長理論)とがあります。
- 経済成長の帰結はどのように社会に波及していくのか?
- 経済成長が所得分配や雇用、生活水準にどのような影響を及ぼすのか、また成長が停滞する要因や成長の限界は何かといった分析にもつながります。
代表的な理論の概要
- 古典派的成長理論 (マルサス、リカードなど)
- 農業生産などの自然要因や人口原理に着目。マルサスは人口増加が限界を迎えることで経済は停滞する、と論じました。
- ハロッド=ドーマー・モデル
- 資本の蓄積と投資を中心に、所得増加をどの程度投資に回し、どのように生産能力を拡大するかを分析。経済が不安定になりやすい側面も示しました。
- ソロー・モデル (新古典派成長理論)
- 資本蓄積(貯蓄率)・労働力増加率に加え、「技術進歩」を外生的(外部から与えられる)に扱い、長期的には技術進歩が成長を規定すると考えます。
- 資本の限界生産力が逓減する(規模に関して収穫逓減)ことや、貯蓄率の上昇だけでは無限に成長速度が高まらないことを示しました。
- 内生的成長理論 (ローマー、ルーカスなど)
- 技術進歩を経済内の要因(研究開発投資、人的資本、ナレッジ・スピルオーバーなど)から説明しようとするアプローチ。
- 経済活動そのものが技術進歩を生み出すので、政策や制度設計によって長期成長率を高められる可能性を示唆します。
まとめ
経済成長理論の核心は、「なぜ経済は長期的に成長するか(あるいは停滞するか)」を解き明かし、その背後にある資本蓄積や人的資本、技術進歩・イノベーションといった要因を理論的に説明しようとする点にあります。
そして、外生的・内生的いずれの理論においても、成長を規定する最大の要因は「生産性の向上」、すなわち技術進歩や知識の蓄積であるという点は共通しており、この考え方があらゆる成長モデルの出発点になっています。